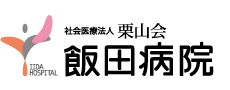循環器内科

当科の特徴
近年の高齢化、生活習慣病の増加に伴い心血管疾患も増加の一途をたどっています。また心臓血管診療は日進月歩であり、カテーテル検査、治療をはじめとしてペースメーカー治療、補助循環装置などの進歩がその基礎を支えています。2013年4月に心血管造影装置、心臓電気刺激装置、ポリグラフ、大動脈内バルーンパンピング(IABP)を更新し、2015年4月には経皮的心肺補助装置(PCPS)、さらには南信地域で唯一の振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム(クロッサーシステム)を導入いたしました。また、2016年4月からは心臓超音波装置、経食道エコー装置の更新を行い、心臓疾患の再発予防、予後改善効果のある心臓リハビリテーションも開始いたしました。これまで困難とされていた透析症例の高度石灰化下肢動脈カテーテル治療などもクロッサーシステムを用いて治療を行っています。
主な対象疾患
狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、慢性心不全、不整脈、弁膜症、その他生活習慣病全般
●狭心症
冠動脈(心臓に栄養を送る動脈)が動脈硬化や血管の痙攣により流れが悪くなって、結果的に心臓の栄養不足が生じる病態です。胸部圧迫感、息切れが典型的な症状ですが、稀に歯の痛みや肩の痛みを生じることがあります。症状は発作的に起こることが多いですが、頻回に起こる場合は不安定狭心症と言い、緊急で対応が必要になる場合もあります。
●閉塞性動脈硬化症
動脈硬化により末梢の血管が細く血流不足になることで生じる病気です。主に下肢の動脈の流れが悪くなり、歩き始めはいいのですが、数十mくらい歩くと足がだるくなり痛みを生じる跛行(はこう)症状を認める場合があります。
●心不全
心臓に負担がかかり、呼吸困難や全身のむくみを生じる病態です。狭心症や弁膜症、不整脈などが原因でおこる場合が多く、急性期には入院治療が必要になります。
診療実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カテーテル検査 | 262 | 245 | 212 | 150 | 115 |
| 冠動脈治療 | 109 | 116 | 91 | 52 | 66 |
| 末梢動脈治療等 | 36 | 19 | 22 | 21 | 25 |
| ペースメーカー 移植術 |
34 | 30 | 24 | 31 | 18 |
| ペースメーカー 交換術 |
7 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 経皮的心筋焼灼術 | 34 | 44 | 42 | 41 | 43 |
| 下肢静脈瘤治療 | 25 | 47 | 47 | 43 | |
| 心臓CT | 787 | 696 | 348 | 267 | 248 |
| 下肢CT | 139 | 137 | 69 | 65 | 46 |
診療スタッフ
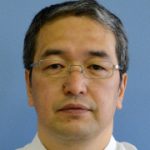 |
唐澤 光治(循環器内科部長)専門領域 |
 |
伊藤 健一(循環器内科副部長)専門領域 |
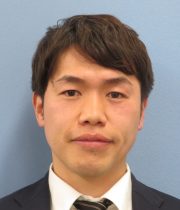 |
竹内 和航(循環器内科医長)専門領域 |